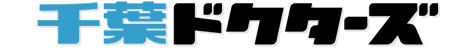岩松 晃弘 院長
AKIHIRO IWAMATSU
なるべく抜かない、削らない。
むし歯にさせない歯医者さん
日本大学歯学部 卒業。東京医科歯科大学歯学部付属病院う蝕制御学分野 入局。千葉県の大手医療法人にて勤務。2008年に『ウニクス成田歯科』を開業。2019年には『はなのき台みんなの歯科』を、そして2024年に『千葉ニュータウンおとなこども歯科』を開業。

岩松 晃弘 院長
千葉ニュータウンおとなこども歯科
印西市/牧の原/印西牧の原駅
- ●歯科
- ●小児歯科
- ●矯正歯科
地域の歯科医院として多くの方の支持をいただいてきた知識と経験を結集して

叔父が歯科医師でした。その叔父の存在があって、さらに手に職をつける時代ということもあり、歯科医師の道を選択したのです。大学卒業後は東京医科歯科大学(現:東京科学大学)のう蝕制御学分野に在籍しました。一般の患者さんに向けては「むし歯外来」となっていたところですね。お口には様々な疾患がありますが、歯科医師として、まずはむし歯をきれいに治せるようにと考えての選択でした。
退局後は千葉県の医療法人勤務を経て、2008年に成田で最初の医院を立ち上げ(ウニクス成田歯科)、次いで2019年にはなのき台に2院目を(はなのき台みんなの歯科)、そして昨年(2024年)の11月に『千葉ニュータウンおとなこども歯科』をオープンしました。当院はショッピングモールの中に位置していますので、もちろん小さなお子さんを抱えたお母さん、お父さんが多いのですが、ご高齢の方も少なくありません。私は成田で開院した時から幅広い層の方々を拝見してきましたので、その培ってきたスキルと経験を生かし、地域のあらゆる人のお口の健康に貢献していきたいと考えています。
怖くなく、出来るだけ痛くない歯医者さんを目指して

正直なところ、歯科医師になるまで、歯医者さんには怖いイメージを持っていました。私の子どもの頃は「無理やり押さえつけられて」というのも珍しいことではありませんでしたから。その時拘束されたゴムの臭いは、今でも忘れられません。その辛い経験を生かしてと申しましょうか、できるだけ怖くなく、痛みの少ない治療を心がけています。
「痛み」については、どうしても避けられない面もありますが、「これからちょっとチクっとしますよ」といった細かな声掛けも徹底しています。それから、歯の中は自分では見えないところではありますので、レントゲンはもちろんのこと、口腔内を写真に撮り、その時の状態や「何をどうしたのか」といったことをビジュアルでお見せするようにしています。“わかる”ことで、痛みが緩和することもあると思うんですね。
当院は「RODY」公認の歯科医院です。楽しみとまではいかないにしても、お子さんが構えることなくいらしていただけるような雰囲気づくりにも気を配っています。
出来るだけ削らず、神経を大切にする治療

歯の中には神経というものがあります。私が子どもの頃は何でもかんでも取っていたものですが、歯の寿命を考えればとらないのがベターであり、なるべく温存できるような治療を心がけています。大学の医局では、そうした治療を専門に学んできました。当時とは材料などは違っているわけですけども、考え方などは今に通じるものがありますし、当院の勤務医の先生にも、まず神経を残せる治療をしっかり身につけてもらうよう指導しています。
たとえ神経を取らざるを得ない場合も、いわゆる根管治療を丁寧に行うことによって歯の寿命を延ばすことは可能です。そのために有用なのがCTです。根の中は曲がっていたり、先が枝分かれしていたり、千差万別です。その治療は一筋縄ではいかない面がありますが、CTで見れば、三次元的に根の状態を把握することができます。車で言えば、ナビゲーションシステムがあるようなものですね。あらかじめ、どのような方法で治療を進めるかを把握できますので、治療の精度もスピードも以前と比べれば飛躍的に上がりました。当院ではできるだけ削らず、神経を大切にする治療を志向しています。
歯の大切さやその価値に気づいていただくことも歯科医師の役割
治療が一通り終われば、次はメンテナンスということになります。歯を持たせるためには治療の精度も重要ですが、やはり定期的にメンテナンスを受けていただくことが重要です。プロフェッショナルである私たちにしても磨き残しは必ずあるものですから、それをクリーニングできれいに取っていくことが大事なんですね。
とは言え、歯の大切さは、健康な時は忘れがちになるものです。ですから、歯の大切や価値に気づいてもらうことも私たちの重要な役割と認識しています。メンテナンス時には、ご自身の歯の状況がわかる資料をお渡ししています。歯周病の進行度合いがわかる歯周ポケットというものがありますが、その深さがどれくらいか、一目でわかるような資料です。万一、病気が起こったとしても、定期的に診させていただければ、早期のうちにアプローチできますので、早期発見・早期治療を可能にする意味でもメンテナンスは重要です。
これから受診される患者さんへ
繰り返しになりますが、当院では神経を大事にする治療と、それに続く歯を残すための予防歯科を重視しています。いきなり治療するなんてことはもちろんありませんので、お口で何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
※上記記事は2025年2月に取材したものです。時間の経過による変化があることをご了承ください。
岩松 晃弘 院長 MEMO
- 出身地:千葉県
- 出身大学:日本大学歯学部
- 趣味:筋トレ、ゴルフの打ちっ放し
- 好きな音楽・アーティスト:洋楽/オアシス、Mr.Children
- 好きな場所:千葉県
- 座右の銘:「No Pain No Gain」
岩松 晃弘 院長から聞いた
『口呼吸』
口呼吸がもたらすデメリットについて
1.「口腔内の乾燥」
鼻呼吸に比べて口呼吸は唾液が分泌されにくくなり、口腔内が乾燥します。これにより、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
2.「口臭」
口が乾くことで、バイ菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因となることがあります。
3.「歯並びや顎の発育への影響」
長期間の口呼吸は、顎の成長や歯並びに悪影響を及ぼし、歯列不正や顔の形にも影響を与えることがあります。
4.「睡眠の質の低下」
口呼吸は、いびきや睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めるため、睡眠の質が悪化することがあります。
5.「気道感染のリスク」
鼻呼吸は空気をフィルターする役割や加湿する役割を果たしますが、口呼吸ではこれらの機能が低下し、喉や気管支の感染リスクが高まることがあります。
6.「栄養吸収への影響」
口呼吸は、食事の際の咀嚼や唾液の分泌にも影響を与え、栄養の吸収に悪影響を及ぼすことがあります。
口呼吸になってしまう要因としては様々なものがありますが、鼻炎などとともに姿勢が大きく影響しているものと考えられます。今の時代、みんながスマホをのぞいていますよね。すると首が前に出る状態となり、口呼吸を誘引しているのではないか、とする見方があります。そのほか、外で遊ぶ機会の少なさだったり、環境が原因として大きく考えられる状況では、口呼吸は現代病といっても差し支えないかもしれません。先に挙げたデメリットを軽減するためには、できるだけ鼻呼吸を心がけることが重要です。必要に応じて、専門医の相談を受けることもおすすめです。
グラフで見る『岩松 晃弘 院長』のタイプ
 |
穏やかで明るく話しやすい先生 |  |
||||
![]()
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
![]()
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
 |
穏やかで明るく話しやすい先生 |  |
||
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
|||
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
CLINIC INFORMATION

千葉ニュータウンおとなこども歯科
岩松 晃弘 院長
印西市/牧の原/印西牧の原駅
- ●歯科
- ●小児歯科
- ●矯正歯科
| 医院情報 | 院長紹介 | 求人 | MAP | 徒歩ルート |
| 医師の声 | 患者の声 | お知らせ | WEB予約 |
オンライン 診療 |
| 電話 | 03-6426-5933 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | |
| WEB | |
| 休診日 |